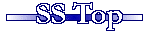 |
|
東京の命運を賭けた闘いから、約2年。 師走の賑わいをみせる雑踏で、京一と醍醐はかつての恩師と遭遇した。 「あれ、犬神…」 「…よお」 濃い灰色の大きなコートを羽織り、伸びかけた髪を無造作に後ろで束ねている犬神は、白衣の格好の時とは随分と雰囲気が違って見える。 …格好のせいだけではないな、と醍醐は感じた。 どことなく、自分達が学生をやっていた頃より柔らかな空気を纏っている。 まあ、とてつもない問題児共が揃って卒業したわけだし、あの強く張り詰めた雰囲気も和らいで当然か、と1人納得する。 「何だ蓬莱寺、中国に鍛練に行ったんじゃなかったのか?」 皮肉っぽい口調は変わらず、犬神が話し掛けた。 「親が『盆と正月くらいは帰ってこい』ってうるせーんだよ」 負けじと、京一もいつもの反抗口調で返す。 だが、犬神の方はその言葉をうけて、ふっと微笑んだ。 「そうだな…そんな時くらい、みんなに顔をみせた方がいいだろう…」 「……」 毒気を抜かれて、京一はきょとんとしている。 2、3回瞬きをした後、こそっと醍醐に耳打ちする。 「…なあ、犬神の奴、なんか丸くなってねえか?」 「ああ…俺もそう思った…」 「寄る年波ってやつかな」 「…誰がだ」 さすがに今の会話が聞こえたのか、犬神がコン、と京一の頭を叩く。 「ってえ…ああ、いやいやセンセイ、御身体の具合でも悪いのかなあとか…なあ」 ごまかすようにへへっと笑う京一。醍醐の方は苦笑いを浮かべて、犬神に頭を下げた。 それからふと思い付いたように、醍醐が犬神に声をかける。 「先生、これからお時間があるようでしたら、一緒に飲みに行きませんか」 「っ…おいおい醍醐っ…」 横にいた京一が驚いた声をあげ、醍醐の脇腹を肘で小突いた。 「なに考えてんだよ」 「いや、どうせだから他の連中も呼んでみんなで飲むのもいいかと思ってな」 「…そりゃ…いいけどさ」 何も犬神から声をかけなくても、とでも言いたげに京一は複雑な表情を浮かべている。 犬神は少しだけ考える素振りを見せたが、すぐに醍醐に答えた。 「…おさそいは嬉しいがな…残念だがやめておこう」 「あ、駄目…ですか。すみません」 改めて頭を下げた醍醐に、犬神はつけたした。 「家で女房が待ってるもんでな」 「「!?」」 あまりに意外な台詞に、2人はびっくりして目を見開いた。 「まさか…」 「結婚…したのかよ」 唖然としている2人に、犬神は「じゃあな」と声をかけてその場から去ろうとした。 「あ、お、おい!ちょっと待った犬神!」 慌てて京一が声をかける。 犬神が振り向くと、その顔を覗きこみ、まるでいたずらっ子のように目を輝かせた。 「なあ、ちょっとだけ…遊びいっていいか?」 「こら京一!」 「んだよ醍醐、お前だって興味あんだろ?一緒にいこうぜ」 「い、いや…しかしだな」 何と答えていいかわからず狼狽する醍醐。 犬神は、やれやれといった笑いを浮かべて言った。 「別に構わんが、なんのもてなしもできないと思うがな」 「やー、それこそ構わねえって♪」 「す、すみません…」 雑踏の中へと歩き出した犬神に、嬉々として京一がついていく。その後を、好奇心に負けた醍醐がおずおずとついていくのだった。 「相変わらずだなー…犬神のアパート」 自分達が学生の頃から変わっていない安アパートの前で、京一は素直な感想をもらした。 「…奥さんいるんならもうちょっといいトコ住めばいいのに…あ、でも教師の安月給じゃここが限界ってトコか?」 呟くや否や、もう一度頭をコン、と殴られる。殴ったのは醍醐のほうだ。 「…余計な事言いすぎだぞ京一…」 未だにためらいのある醍醐は、犬神の顔色をそおっと伺った。 しかし、犬神は別段気にする様子もなく言った。 「まあ、そんなとこだな」 「ほうらみろ」 珍しく怒られないので(怒られて当然だとは思うが)、京一はご機嫌である。 日も暮れて、辺りは薄暗くなっている。その中で、犬神の部屋の窓からもれるあかりはその部屋に人がいる事を物語っていた。 「…ふうん…なんかこういうのって、いいな…」 あかりの灯った部屋の玄関の前に立つ犬神が、何だか幸せそうに見える。茶化すのも忘れて、京一と醍醐は犬神が玄関の戸を開けるのを待った。 「…ただいま」 玄関を開け、低く響く声で中に呼びかける。 「あ、おかえりなさい」 嬉しそうな声が部屋の中からかえってくる。 …しかし。 「…え?」 今の声は。 京一と醍醐、2人の思考が停止した。 ひどく馴染みのある、男の声だった。そうだ。真神にいた頃は、この声と共に語り、遊び、戦った… 「…ひー…ちゃん?」 ぱたぱたと玄関先まで歩いてくる音が聞こえる。 そおっと…犬神の後ろから玄関の中を覗きこむ。まるで怖いものみたさ。 彼らを出迎えたのは、間違いなく…龍麻であった。 「先生お疲れ様……あれっ?」 龍麻は、犬神の後ろで呆然と立ち尽くしている2人を見つけた。 「京一!醍醐!」 京一も醍醐も、名前を呼ばれた事に気付かなかった。ただ、出てきた龍麻の格好を見て…固まっている。 龍麻の髪は濡れて光っていた。いつもまるで人を惹き付けすぎる瞳を隠すかのようにしていた長い前髪は、濡れたままかきあげられていて、その双眸が露わになっている。 大き目の洗いざらしのデニムのシャツと、丈が短めのズボン。白い足首が浮かび上がって見える。 冬にしては随分と薄着だと感じるその格好に、とどめ。フリルこそついていないが、白いエプロン姿。 『す、すまん龍麻!お、俺はそのっわざとお前のそんな姿を見ようと思っていたわけでなくっ…いや、そもそも犬神先生のとこに行こうと言い出したのは京一でっ…い、犬神先生と…お前が、その…あー……』 『なななんてカッコしてんだひーちゃん!それってもしかしなくても風呂上がりってやつか!んでエプロン?そんな旦那を悩殺する若奥さんみてーな真似…ってえーとまてよ、いいのかそれで…っていやちょっとまてそのひーちゃんがどうして犬神を悩殺すんだよってーか、わ、若奥さん??奥さんなのかひーちゃん…ってどわあっ!』 硬直したまま頭の中がぐるぐるしてパニックに陥る2人。…最後の京一の(心の)悲鳴はというと、てっきり2人にそんな姿を見られて慌てて取り繕うなり隠れるなりすると思っていた龍麻が、駆け寄ってきて京一に抱きついたからだった。 「京一!久しぶりじゃないか!何時帰ってきたんだよ!連絡くらいよこせよ」 そんな風に抱きつくのは、高校時代にお互いよくやった、単なる(他人から見ればかなり過剰な)スキンシップ。 にも関わらず。その行動に京一の頭の中は真っ白になった。 自分より少し背の低い龍麻の髪や身体から、ふわりと石鹸の香が立ち昇り、鼻をくすぐる。 寒空の中、冷え始めた自分に触れてくる暖かい身体。 自分のこの腕を背中に回して思い切り抱きしめたら、きっと柔らかいに違いない… 『って…ま、待て俺!落ち着け!旦那が、旦那が見てるんだ奥さんっ!いくら据膳でもこの状況じゃ俺はひーちゃんを食うわけには…嬉しいけどこういう事は今度旦那がいない時にでもゆっくりと…!』 もはや自分に対するつっこみすらままならなくなり、京一の腕は龍麻を引きはがそうとしているのか抱きしめようとしているのか判らない形のまま止まっている。 「…感動の再会は終わったか?」 犬神が、その京一の狼狽ぶりを見て抑え切れない笑いを漏らした。 「まあ、そんなトコに突っ立ってても冷えるだろう。とりあえず上がっていけ、お前等」 「あ、そうですね、すいません」 ゆっくりと、龍麻は京一から手を離した。しかし京一は固まったままだ。 龍麻は犬神の後について玄関に入る。そこで一旦振り向くと、何故か動こうとしない2人を見やり、怪訝そうな表情を浮かべながら手招きした。 何とか我に返った醍醐が、後ろから体当たりをするように京一を押しやって前に進ませ、そうしてようやく2人とも犬神の部屋へと上がった。 「京一も醍醐もコーヒーでいいか?」 流しの方から、龍麻が顔を覗かせて声をかけてくる。 「ん?あ、ああ…」 上ずった声で京一が生返事を返した。 先程のエプロン姿で流しに立つ龍麻が見える。 犬神は着ていたコートを脱ぐと、その辺に放り投げてテーブルの前に座った。 コーヒーを人数分運んできた龍麻が、それを見て文句を言う。 「先生、だからコートがしわになりますってば」 「わかったわかった」 苦笑しながら、ハンガーにコートをかける犬神。 なんかもうどう見ても…新婚。 の、筈なのだが、さっきから京一も醍醐も奇妙な違和感を感じていた。 コーヒーを啜りながら、犬神は龍麻に声をかける。 「悪いな、緋勇。こんな事までさせて」 「いえ、構いませんよ」 『…あれ?』 京一と醍醐は顔を見合わせた。 『今、犬神ってひーちゃんのこと「緋勇」って呼んだ…?』 『そういえば、龍麻は「先生」って呼んでるな…』 違和感は、それだ。 いくらなんでも、お互いその呼び方は…ないんじゃないのか? ……違うのか? 京一の隣りにぺたんと龍麻が腰を下ろす。 「あ、あのよお、ひーちゃん」 妙に落ち着かない素振りで、京一が隣りを向いて話し掛けた。 「その…犬神のさあ、奥さんって…」 「あ」 言った途端、龍麻はいきなり立ち上がった。 何か悪い事言ったか?やっぱ聞いちゃいけなかったかっ?と、びくついている京一に、龍麻は納得したというような表情をむける。 「そっか、京一たち、見にきたのか。なるほどな」 「そう言えば、今どうしてる?」 犬神が目を細めた。 「寝てます。さっき洗ったから…疲れたらしくて。あ、でも今連れてきます」 そういうと、龍麻は隣りの部屋へと消えた。 「……?」 何の話だ…?と、話についていけない2人は神妙な顔をした。 程なくして、隣りの部屋から声が聞こえる。 「たまちゃん、よかったな。旦那様のお帰りだぞ」 そして、からっと隣りの部屋の襖が開いた。 …龍麻が毛玉を抱えている。 と、その毛玉はもこもこと龍麻の腕の中で形を変えた。 それは、茶色い柔らかい毛がふわふわの、ポメラニアン。 小さな顔に、ビーダマのような真ん丸い真黒い目がついている。 そのつぶらな瞳が犬神を見つけると、嬉しそうにキュン、と鼻を鳴らした。 犬神が、おいで、というように両手を広げると、それは龍麻の腕からピョンと飛び出し、犬神の膝の上へとかけていった。 「…あれ…」 突然の出来事に、京一も醍醐もぽかんとしていた。 「熱烈だろ?もーすげーラブラブ」 龍麻が満足そうにその様子を眺めている。 「じゃあ、あれが…ひょっとして」 「ああ、だから、犬神先生の奥さん」 「―――そういうオチかよー!」 脱力する京一に、喉の奥で笑いながら犬神が言った。 「ん?…なんだと思ったんだ?」 「……てめえ…わかっててやったな!ちっくしょー!」 真っ赤になってそっぽを向く京一。醍醐も、してやられたと苦笑いを浮かべて頭を掻く。 「まったく…先生も人が悪い…」 「ふ…すまなかったな」 膝の上のポメラニアンはご機嫌らしく、犬神に耳の辺りを撫でてもらってそのボンボンのようなしっぽをふさふさと振っている。 「あーあー、犬神にお似合いだよ」 ふてくされた京一が、皮肉のように呟く。 「すごいよな」 その龍麻の言葉にやけっぱちで相づちを打とうとしたが、やけに声が真剣なことに気が付いてふと龍麻の顔を覗きこんだ。 龍麻は笑っていなかった。 真面目な顔で、2人にそっと話し掛ける。 「…犬神先生になつく動物なんて、俺は初めて見る―――」 「え…」 「あ…」 言われて、ようやく気付いたように口を開いた。 そうだった。人より遥かに感覚の鋭い動物達は、犬神の中の猛獣を感じ取れるのだろう。どんなに人に馴れた動物でも、決して犬神の近くには寄らない。頭の悪い動物に至っては、牙を剥き威嚇することも往々にしてある。 「本当に、たまちゃんは犬神先生が好きなんだろうな」 「…そっか」 京一は改めて、不思議な想いで犬神の元にいるその犬を見つめた。 真黒い瞳と目が合ったので、取りあえず呼んでみる。 「えと、たまちゃん」 クウン、と返事が返ってきた。頭がいい。 「…犬神、ちょっと撫でてみていいか?」 真面目な顔で旦那にお伺いをたてる京一に、犬神はとうとう吹き出した。 「くっくっ…ああ、構わん」 「お、おう」 手を伸ばすと、興味深そうに鼻を寄せてきた。そのふわふわの毛を撫でてやると、先程抱きついてきた龍麻と同じ石鹸の香りがする。 『そっか…洗ったっていってたもんな…』 さっきの風呂上がりのような状況は、そのせいだったのだろう。 …あれ?待てよ? 「ところでひーちゃん…今更なんだけど、犬神んちで何してんだ?」 京一が龍麻の方に向き直って尋いた。 「俺?俺は有能な日雇い家政夫」 龍麻は胸をはってそう答えた。 「家事全般ならなんでもできるからな、俺。今、大学冬休みだし、先生に頼まれて今日みたいに留守番とかしたり」 ちなみに今は夕飯作ろうとしてたトコ、と龍麻は白のエプロンをひらひらとさせて見せた。 「なるほど…バイトみたいなものか」 「そーいうことだ。…時給安いけどな」 最後の一言はこそっと、龍麻は醍醐にそう答える。 「―――ああそうだ、蓬莱寺、醍醐。どうせだからお前等もここで飯食っていけ」 膝の上で眠そうに欠伸をしたポメラニアンをそっと抱えて隣りの部屋に移し、犬神は2人に声をかけた。 「え?いいのかよ」 「まあ、せっかく来てくれたんだしな」 そう言ってまた犬神は可笑しそうに小さく笑う。 結果として犬神に振り回されてしまった京一と醍醐は、流石にその夕食の誘いを遠慮する義理はなかった。 「そーだよなあ…じゃ、ごちそうになるぜ」 「ああ。と、言うわけだ。緋勇、お前の分も含めて夕食は4人分作ってくれ」 「…先生、追加料金もらいますよ…」 ふざけながらも龍麻は楽しそうに微笑むと、流しの方へと向った。 結局、龍麻の作った軽い夕食と(何故軽いかというと、材料がそんなに揃っていなかったから)勢いでビールも少しご馳走になって、2人は帰途についた。 「…で、ひーちゃんはまだ帰らないんだって?」 「ああ、あと洗濯の仕事が残ってるって言ってたな」 「かわいそーになあ、ひーちゃん。コキ使われちゃって」 あーでもひーちゃんの手料理、久々に食ったなー、といって京一は笑った。が、どことなくいつもの元気がない。 そのまま2人とも、暫く沈黙して歩く。 何か声をかけようと醍醐が口を開きかけた時、ため息交じりに京一が呟いた。 「たまちゃん…か…。可愛かったよなあ…ちくしょううらやましいぜ…」 そのいきなりの台詞に、醍醐は目を丸くした。そして思わず吹き出す。 「どうした京一。そんなに気に入ったのか?その…犬神先生の、奥さんが」 「だってよお!あんなおっきい目であんなふかふかしてて、呼ぶと返事までしちゃってさ!こう、きゅーってやりたくなるじゃん!」 熱弁しだした京一をみて、醍醐はそっと安堵のため息を漏らした。 『心配は、無用か』 「京一、人の奥さんに横恋慕は感心できんぞ」 「ちぇー…わかってるって。…でもいいよなあっ」 そのまま笑い合いながら、京一と醍醐は別れ道に着いた。 「じゃな」 軽く挨拶をして立ち去ろうとする京一に、醍醐はつい声をかける。 「あ、京一」 「ん?なんだよ」 「…いや、何だ…明日にでも、本当にみんなを呼んで飲みに行かんか」 「何だよ醍醐、マジな顔して何言うかと思ったら、そんなに飲みたいのかよ!」 京一はひとしきり笑うと、パンッと醍醐の背中を叩いた。 「おし!んじゃ明日はみんなでパーッと行こうぜ!大将、セッティングよろしくなっ!」 「―――ああ、まかせろ」 変わらない京一の明るさに安心したように醍醐は笑い返した。 角を曲がると、京一の姿が見えなくなる。それを確認してから、醍醐は深くため息をついた。 「まったく…先生も、本当に人が悪い…」 肩を落として呟く。 どんなにふざけていたって、判るものは判る。龍麻に会って…確証した。 犬神が現在纏っているあの柔らかい空気。 あれは、龍麻が持っている空気と全く同じものだ。 つまりは…そういう事なのだろう。 自分とは比にならない程の強さと、優しさを備えた心地よい空気。 少なからず憧れ続けたもの。だからこそ…気付いてしまった。 …京一には伝えないでおこう…と、醍醐はこの事を自分の胸にしまいこむ事にした。 もっとも、気付いているかもしれない。 なんだかんだ言ったって、龍麻の一番近くにいたのはまごうかたなき京一だったのだから。 角を曲がると、醍醐の姿が見えなくなる。京一は、それを確認すると空を仰いで呟いた。 「嘘が下手だぜ…醍醐も犬神もひーちゃんも…」 判らないわけが、ない。常に自分と一緒にいた空気。 その空気を共有できる程、ひーちゃんて犬神の近くにいるんだなあ…と感じた。 …悔しかったけど、怒りはわいてこなかった。からかわれて、騙されてる筈…なんだけどなあ。 まあ、その理由も実はイタイほど判っている。認めるのが癪なだけで。 「…そういや、たまちゃんてホントに可愛かったなあ…」 人の奥さんに横恋慕は感心できんぞ、という先程の醍醐の冗談めいた台詞が頭を過ぎる。 …判ってるって。 でも、横恋慕ってわけではない。横じゃなくて横じゃなくて。ずっと、想ってて。 でもそれでもやっぱりこーいうのって横恋慕になるか?ちぇ。 家政夫っつーより、ひーちゃん…通い妻なんだろうなあ。 しかもあのたまちゃん。犬神とか気付いてんのかどーだかわかんないけど、あれは…ひーちゃんにそっくりなのだ。 あの瞳とか、仕種とか。頭もいいし。 はっ!てことはもしかしてたまちゃんて、ひーちゃんと犬神の子供! 「って馬鹿か俺は!」 とりとめもなく想像で遊んでいた自分に自分でつっこみをいれる。 ふ、と一旦息をついてから、もう一度空を仰いだ。 …今度、旦那のいない時狙ってマジで遊びに行こうかな。 浮気まではしてくれないだろうけど、今日みたいに抱きついてくれたりすると嬉しいかも(俺の理性がもてば)。 「ま、なんにしてもあんなニブチンの醍醐にもバレるくらいだ。飲み会になったら他の連中もさぞ驚く事だろーよ♪」 へへっ、と声に出して笑う。 龍麻の笑い顔を、思い出した。 ―――まあ…いいや。幸せそうだったから。 認めざるをえないよな。 そう、心で呟いた。 龍麻は、冷蔵庫の前でしゃがみこんで、中を確認している。 「先生…朝飯の材料ないですよ、流石に」 そう言って振り向こうとして、突然後ろから抱き締められた。 「わあっ…先生っ」 慌てて身を捩ると、犬神はその反応を楽しむかのように笑いを浮かべている。 照れて困った表情を見せた龍麻の唇に、軽く自分の唇を合わせる。 たかがこれだけのキスに、未だに龍麻は硬直して真っ赤になってしまう。 それがまた可笑しくて可愛くて、犬神は龍麻を抱き締める腕に力を込めた。 龍麻はまだ困った顔をしている。 「どうした?緋勇」 「…バレてんだろうなあ…と思って…」 別に隠したいわけじゃないけど、と龍麻は呟いた。 犬神はその言葉に暫く沈黙していたが、やがて抱き締めた腕を緩めて龍麻を正面から見据えた。 「いい友人だな…」 「―――はい」 京一も醍醐も、下手な嘘くらいすぐ看破してしまう程、自分の事を判ってくれている。 それを誉められて、龍麻は嬉しそうに微笑み、自分に回された腕に身体を預ける。 「それにしても…あれは、サービスしすぎだ」 「え」 それが京一に抱きついた行動の事だと気付き、龍麻はおそるおそる犬神の顔を上目遣いに見た。 「…先生、怒ってます?」 「いや」 そんなのは犬神の表情を見れば一目瞭然なのだが、つい龍麻は尋いてしまう。 犬神はくしゃくしゃと龍麻の柔らかい髪を撫でた。 「…も、もしかして…妬いて…くれたとか」 最後の方は小声で囁くようにして、龍麻は俯いた。 しかし、犬神の答えが返ってこない。 不安げな表情を露わにして、そろそろと龍麻が顔を上げると犬神は意地の悪い笑みを浮かべた。 そのままぐいっと顎を掴むと、今度は深く口付ける。 「ふっ…んぅ……」 ゆっくりと舌を絡め、柔らかな唇を軽く吸い上げる。 角度を変えてまた舌を交わらせ存分にその感触を堪能したあと、静かに龍麻の唇を解放した。 「……は…」 龍麻は脱力しかけた身体をなんとか自分で支えて、大きく息をつく。 と、犬神に突然ひょいっと抱き上げられた。 「えっ…うわ、ちょ、ちょっと先生っ」 慌てる龍麻の耳元に唇を寄せて、犬神は低く呟いた。 「わかっててやったんなら…お仕置きだな」 「ええっ!」 暴れ始めた龍麻を軽々と抱きかかえ、犬神は奥の部屋に移る。 敷いてある布団の上にころんと龍麻を転がすと、その上に覆い被さった。 「待った!待ってください先生っ!た、たまちゃんお向いさんに帰してこないとっ…」 そう。たまちゃんは、犬神のアパートの向いの家の犬なのだ。 本当に犬神が気に入ったのか、ちょくちょくこの部屋に遊びに来るのでたまに世話をしてあげる。 アパート内では飼うわけにはいかない。ので、夜には向いの家に連れていってやる。 …たまちゃんが、通い妻…なのである。 自分の腕の下でもがく龍麻を簡単に抑えつけ、首筋に顔を埋め息を吹きかけると、龍麻の身体がビクン、と跳ねる。 「安心しろ、後で俺が連れて行くから」 犬神はそう耳元で告げると、尚も反論しようとする龍麻の口を自分の唇で塞ぐ。 そして今度こそ、龍麻の身体から完全に力が抜け抵抗できなくなるまで…深く深く口付けを繰り返した。 当のたまちゃんは、犬神達が奥の部屋にやってきた時点でトコトコと隣りの部屋に移動し、近くにあった座布団の上にコロリと横になった。 そして大きく欠伸をすると、澄ました顔をして座布団の上で寝てしまう。 幸せな彼等の邪魔をする気は…ないようだ。 End. …ヘンなオチ… |
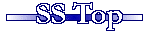 |