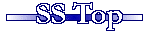 |
|
いつもなら晴れた夜空を支配しているはずの月が,今夜は闇に沈んでいる。 本来なら星のみがその空を彩るはずの新月の夜も,都会では空に近づこうとしているビル達が挙って空を明るく照らしている。 そんな中,犬神は自分のアパートから少し離れた小さな公園に来ていた。 人影が全く見当たらないその公園には,頼りなさそうな街燈がひとつだけついている。 その街燈の下にある古いベンチに深く腰掛けると,犬神は懐から煙草を取り出して火を点けた。 街燈の明かりの中で紫煙がゆらめいて,犬神はそれを面白くなさそうに眺める。 ―――――人工の明かりというのは,どうも好きになれない。 月や太陽の様に力を持った光ではなく,ただそこを照らしているだけのものだというのに,今の自分はその光がなければ暗闇の中を見通すこともできない。 犬神にしてみれば,夜目が利かない自分というのは,なかなか不甲斐ない。 もっとも,視覚に限らず外に向う感覚のすべてが自分の思うようにはならない…それが,新月の日だ。 こんな日は何もかもやる気が起こらない。現に,昼間の授業なんかは面倒くさくてしょうがなかった。 自分が生徒なら,間違いなく屋上で昼寝だ。サボリだ。―――生徒に文句は言えない…。 普段なら散歩をする気力すらない筈なのだが,それでも今日は珍しく,気分転換に緑のある公園へと足を運んでみたところだった。 煙草を一本吸い終わり,犬神は次に何をしたものかと公園を見渡す。 ふと真ん中にある芝生の茂った広場に目をやると,犬神は,本日の鈍重な自分の感覚が見事に自分を裏切っていることを知って苦い顔をした。 誰もいないと思っていたこの公園には,先客がいた。 芝生の上,薄暗い街燈の光が届くか届かないかのところに人が一人寝転がっている。 満月期の自分ともなれば,今自分の座っているここからでもその人物の格好や息遣い,果ては『気』の類まで手に取るように判るだろう。第一,公園に来た時点でその人物の存在に気付く筈だ。 だがしかし今の犬神には,多分人間だろう…程度しか判別できない。『気』も感じられないあたり,極端な話生きてるのか死んでるのかすら判らなかった。 無造作に近づいてみる。面倒なので気配を殺すことも足音を消すこともしていないのだが,その人間はぴくりとも動かない。 格好が判別できるまで近づいて,犬神は頭を押さえた。 真神の学ランだ。 芝生に足を踏み入れて顔を覗きこめる位置まで近づき,犬神はさらにため息をついた。 規則正しい寝息が聞こえる。 どうやら爆睡しているらしいその生徒の髪の毛を軽く引っ張って,声をかけてみた。 「おい,緋勇」 「………んん?」 起こされて,芝生の上に転がったまま,その生徒――緋勇龍麻は大きく伸びをした。 思い切りのいい欠伸をして目を擦ると,ようやくその黒い瞳が開かれた。だがまだ半開きで,如何にも眠そうである。 「――――あれ,犬神先生…」 「…あれ,じゃない…」 「おはようございます」 「…おはようでもない…」 「…む…」 何だか状況把握が上手く出来ていないようだったが,犬神は敢えて聞いた。 「で,何をやっているんだお前は…こんな所で」 「―――…ああ,そうだ。散歩…してたんですよ。で,ここがなんか気持ち良さそうだったもんで」 こう,ごろんと…と龍麻は寝転がったままで説明した。 「…犬かお前は…」 「…先生がいいますか…」 その言葉に犬神は僅かに眉を上げ,ふん,と唸る。 自分が人ならざる者であることは薄々気付かれているらしいが,龍麻はお構い無しに自分に接してくる。 それは別に疎ましいものではなく,むしろ下手に避けられるよりは龍麻の事を「見ていやすい」。 ただ…避けられるのも当然である事に対しこの状況というのは,逆に自分の方が龍麻の存在を危惧しなければならないのかもしれない。 だが実際の所は自分も…――――― そんな事を散漫に考えていた犬神は,龍麻に突然腕を強く引っ張られて芝生の上に転がってしまった。 こんな悪ふざけに対して咄嗟に行動することも出来なかった自分に呆れつつ,犬神は衣服の裾を払って起き上がろうとしたが,龍麻がもう一度袖を掴んで引っ張った為に,今度は尻もちをついた。 「…おい緋勇…」 「いや,これで先生もご同類」 そう満足そうに言うと,再び龍麻は芝生の上に転がって夜空を見上げた。 「絶景なんですよ,ここ」 「………」 芝生の上に座りこんでしまっている犬神は,ここまで来たら「ご同類」もよかろう,と改めて龍麻の隣に腰を降ろし,ゆっくりと横になってみた。 「…なるほどな…」 ここの公園は四方が小高い広葉樹に囲まれていて,芝生の上に寝転がって空を見ると,ちょうど周りの木々に切り取られた空には人工の明かりが殆ど届かない。 星だけが浮かんでいる夜空なぞ,実に久々に見た気がする。 つい,ため息をもらした。 ふと自分の方に視線を感じ首を捻ると,龍麻がこちらをむいている。 「流石に今日はお疲れみたいですね」 「…まあな…」 流石に…という台詞に,どこまで見透かされているものかとも思ったが,犬神はその発言に対する追求は特にしなかった。 「授業も,2ヶ所ほど説明間違ってましたしね」 「…その時につっこんでくれ緋勇」 「教師としてのプライドはどこですか」 「…空の彼方だろう」 「じゃあ…月のあたりですね」 「そうだな」 随分と穿った事を言う…と犬神は苦笑し,改めて中空へと視線を向けた。 大きな目印のない空は特に視点を定めるべき所もなく,ふわふわと視線を漂わせているうちになんだか眠くなってくる。 なるほど龍麻が眠っていたのも良く判る。気持ちのいい倦怠感に包まれながらも,流石にここで自分まで眠るわけにはいかないと霞んだ意識を引き戻した。 寝転がったままでは煙草も吸えないため,大きく息を吸って背筋を伸ばし起き上がろうとすると,龍麻が隣りで呟いた。 「先生,やっぱり新月って嫌いですか?」 「…まあ,有難いものではないな」 率直な問いに,率直に答えた。 ふうん,という聞こえるか聞こえないかの小さな返事に視線を落とすと,龍麻は再び目をつむっている。 そのまま暫く続いた沈黙に,もしかしてまた寝入ってしまったのでは…と思い声をかけようとした時,龍麻がゆっくりと口を開いた。 「―――俺は…好きですよ」 「ほお…?」 「先生が,近いから」 「――――――」 「先生から特別な感じがしなくなるんですよね,一番…」 いつの間にか,龍麻は目を開けて犬神の方をじっと見つめていた。 深い夜の闇と同じ色をした瞳には,今は自分だけが映っている。 ―――こんな瞳で…いつも自分の事を見ていたのだろうか。…自分が龍麻を見ていたのと同じように――― 「…よく『観察』してるな」 その言葉はおそらく,自分が龍麻を見ていたのも『観察』なのだと,犬神自身に無意識に言い聞かせるためのものだった。 それに対して龍麻は,そうですね,と小さく喉の奥で笑った。 「『観察』した限りでは…新月の時の先生は,俺達と同じ…」 そこまで言って,龍麻の言葉は小さくそこで途切れたが,犬神には龍麻の飲み込んだ台詞ははっきりとわかっていた。 「……お前等以下だがな」 一言だけそう返すと,龍麻は困ったように…だが嬉しそうに目を細めた。その顔に,犬神も目を伏せて微笑む。 …今まで見ていた中では,こんな表情は見た事が無かったな… たかがそれだけの事に,犬神は奇妙な充足感を感じる。 「…満月が待ち遠しいですね…」 「…ああ…」 その言葉に犬神は,その充足感が「何」か考えるのを取り止め,もう一度龍麻の隣に寝転がった。 新月は,自分が何をするにも向いていない日だ。考え事だって,しても結局ロクな答えも出ないだろう。そんな事は…それこそ満月の時にでもすればいい。 そう勝手に結論づけて,つい出てきた欠伸をごまかすように大きく深呼吸すると,芝生と土の匂いが鼻をくすぐる。 …月と共に見えなくなってしまっているのは,自分の中の「狼」。プライドの塊のような,孤高の獣だ。 その部分が隠れている今の自分は,「ただの人間」でしかない。 黙って星空を見上げ,耳を澄ますと予想通り気持ち良さそうな龍麻の寝息が聞こえてきて,つい笑いが漏れた。 すぐ近くにいて,ようやく感じる音。この距離が,今の自分と龍麻の…人間同士の,近さ。 「…悪くもないか…」 誰にともなく呟くと,犬神は幸せそうに寝ている隣人を見やり,いつ起こしたものかと逡巡する。 そのうちに自分まで眠ってしまうかもしれない…なにしろ,今日は疲れているんだから… そうは思いつつもこの安穏な空気を壊すのにためらいを感じて,犬神はいつまでも龍麻を起こせずにその寝顔を見つめていた。 その,距離で。 End. …文書くのすげー苦手なんす。 許して下さい。 |
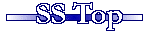 |