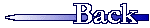 |
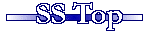 |
|
(後は龍麻の方だな…) 「…」 犬神は妙な胸騒ぎを覚えた。 いくらヒヨッコと言えども、本気を出せば俺と同じくらいの――いや、それを上回る力を持つ龍麻だ。あれくらいの敵でてこずるわけもない。 だが万が一ということもある。 普段なら蓬莱寺達仲間に囲まれ、お互い護り護られているが、今は違う。アイツ一人きりだ。 もし何かヘマをやらかせば…最悪の場合、「死」だ。 (いや、アイツに限ってそんなことがあるはずない) 何を焦っているんだ、俺は…。俺がそんなことを思っていても仕方ないだろう。 ――アイツの力を信じろ。龍麻は必ず勝つ。 (…早く出てこい、龍麻…!) 「グゥォォァアアアアッッッ!!!」 「…!!?」 突如聞こえてきた絶叫に、犬神は辺りを見回した。 (やった…か…?) 響き渡る叫びが掻き消えて行くのと同時に、周囲の霧が完全に晴れていく。 徐々に鮮明になる視界。 「――」 その中で、黄金色に輝く満月の光が龍麻の姿を照らし出していた。 その光景はあまりにも神々しくて、犬神は思わず目を細めてしまう。 「遅かったな、龍麻」 口に出す言葉は短いが、心の中では龍麻の無事をとても喜んでいたりする。それが素直に言えないのも、また犬神ならではか。 (どうやら要らぬ心配だったようだな) 「随分てこずったようだな…」 龍麻の頭を軽く叩く。 「――」 「――龍麻?」 犬神は、うつむいたまま返事をよこさない龍麻の頬に触れた。 ――泣いていた。 熱い涙が瞳から零れ、犬神の指を伝う。 「…僕…先生のことを…殺しました…っ」 それは犬神が闘った<龍麻>と同じ魔物のことを言っているのだろう。 「おい…殺したのは贋者なんだ。泣くことはないだろう」 「でも…先生の姿で――先生の声で『龍麻』って呼んでくれて、すごく優しくって…。贋物ってわかってたけど、どうしても殺すなんて…できなかった…」 ずっとうつむいたまま、龍麻は唇を噛み締めた。 涙で濡れた睫毛が月明かりで輝く。 犬神は零れ落ちる涙を指で拭い取ると、両手で龍麻の顔を上に向かせた。 「もういい。過ぎたことだ、忘れろ…」 「センセ…」 龍麻は震える手で犬神の袖を強く掴んだ。涙は止まるどころか、さらにポロポロと頬を伝っていく。 「怖かった――。先生の手が…僕の首を絞めて――…。どうしたらいいのか、わかんなくなって…っ。それで僕…僕ッ!!」 「そう責めるんじゃない。オマエのしたことは間違ってない…そうしなければオマエが死んでいたんだ」 「でも――」 「それじゃあ聴くが、オマエが死んだら本物の<俺>はどうしたらいいんだ?」 「それはっ――…」 犬神の質問に、龍麻は応えることができなかった。 「龍麻…」 辛そうな表情を見せる龍麻を犬神は優しく抱き締めてやる。 「――頼むから、俺を泣かせるようなことだけはしないでくれ」 「いぬ、がみ…センセ…」 「返事は…?」 「――ハイ…」 龍麻は涙を流しながら微笑んで、そっと犬神の胸に身体を預けた。 こんな龍麻がとても愛らしい。 何の躊躇もなく、愛する者の姿をした魔物を手にかけてしまう冷酷非情な俺。 そんな自分には到底持ち得ない優しさを、龍麻は生まれ持って身につけている。それが羨ましく…そして愛しい。 だからなおさら、俺は龍麻をこの身から離すことができない。決して手放すことなどできない――手放したくないのだ。 犬神は龍麻の髪の毛をそっと掻き上げる。柔らかい髪の毛の感触がとても心地良い。 ふと犬神は、龍麻の首筋に傷があるのを見つけた。 傷の具合からして、先刻の闘いでできたものだろう。薄らと血が滲み出ており、みみず腫れのようになっている。 それは龍麻の白い肌のせいで余計目立って見えた。 「さっきやられた傷か…」 そう言うと、犬神はその部分に唇を寄せた。 「あっ――せんせ…っ」 龍麻の体が小さく反応する。 そのまま、犬神はキツく吸い付き、続けざまに舌で耳の裏側までを舐め上げた。 「…ッ、先…ダメ…ッ」 犬神から逃げようとして手で突っぱねるが、犬神の腕はしっかりと龍麻の腰を掴んで離さない。 「や、ぁ…っ!」 龍麻の瞳から零れる涙を唇で拭う。そして彼の唇に自分を重ね合わせた。 流れる涙で湿ったその唇は、少しだけしょっぱい味がする。 犬神は小さく抵抗する龍麻の口内に舌を差し入れ、彼の舌を弄んだ。 「…ぁ、ふ…んんっ」 犬神のシャツを掴む龍麻の手に力が篭る。二人の口付けの合間からは激しい息遣いが聞こえてくる。 先程の戦闘のせいか、龍麻の精神は異様な昂ぶりを見せていた。 いつもよりもさらに敏感になっている龍麻は、そのキスだけで十分な反応を示してくれた。 「先生…ダメ…こ、んな…トコ、で…ぇっ」 「俺は構わん」 龍麻の意見を無視して犬神はその行為を続ける。 犬神は脱力しきっている龍麻の身体を容易く抱き上げると、近くのベンチへと運び、自分の腿の上に跨がせるような格好で彼を座らせた。 「やぁ、ッ…帰る、ぅ…」 「終わるまでは帰すつもりなどない」 「――ッ、アァッ…!」 龍麻のシャツを脱がせ、胸に口付ける。 月光を浴びたその白い肌は、犬神にはとても眩しく思えた。 胸の飾りを舌で転がし、時には歯を立ててみる。その度に龍麻の声が一段と大きくなり、犬神の欲情に拍車を掛けていった。 もう犬神の中から自制心は失われていた。ただひたすら「龍麻を抱きたい」という思いに任せ、龍麻の身体を弄ぶ。 犬神は休まず手を下へと向かわせた。龍麻のズボンの中にその手滑り込ませ、中で膨らむ欲望の塊を揉みしだく。 「ヤダ、あっ、ああっ…」 下着の中から湿った音が聞こえる。 その行為とはうらはらな優しい愛撫を続けていくうちに、龍麻の抵抗の声は少しずつ嬌声へと変わっていった。 ピクピクと震える体で龍麻は犬神にすがり付いてくる。 「はっ…ク、んっ…」 犬神が龍麻のズボンを引き降ろすのを、腰を浮かせて手伝ってやる。 露になった臀部を優しく撫で回してみる。その滑らかな肌触りは何度体験しても味わい深いもので、犬神は気に入っていた。 それを十分に味わった犬神は、龍麻から出る滴で濡れた指をそのまま彼の秘所へと挿入させた。 何の抵抗もなく受け入れられた指が、龍麻の中を掻き回す。 「――いっ…ハァ…アァッ」 背中を逸らして喘ぐ龍麻の姿は、周囲にある桜と奇妙な程に合っていて、色艶があった。 春風に舞う花弁、揺らぐ龍麻の髪――。ほのかに漂う桜と龍麻の香りが犬神の鼻腔を刺激する。 犬神は自分の下半身が痛むのを感じて、空いている片手でファスナーを下げた。快楽を求めて疼く一物は、龍麻を欲して形を変えていた。 「龍麻――来い」 「ンッ…ふぅ…ァ」 龍麻の腰を掴み、自分自身を秘所へとあてがう。 「ック――あ、んっ」 体の重みで、犬神が龍麻の中へとゆっくり埋もれていく。辛そうに眉間に皺を寄せる龍麻の表情でさえも、今は色気を感じてならない。 「ちゃんと…つかまってろ」 「あんッ…!」 犬神は龍麻の足を抱えて腰を揺り動かした。 「ひ、あ…アアッ――!」 しがみつく龍麻が声を上げる。不規則な呼吸、熱い吐息が犬神の首筋に吹きかかり、ゾクゾクするような快感を覚えた。 「はぁっ、ん…ア、アアッ…ッ」 恋人の小さな喉仏に食いつくように唇を寄せる。そして鎖骨を辿るように舌先で舐めてやると、龍麻は大きく体を捩った。 龍麻が身悶えするのに合わせて、下の部分が締め付けられる。内襞が犬神自身に密着し、二人が動く度に淫らな音を立てていた。 「セ…センセエ…ッ、も…う、ダメェッ…」 「――いけ、龍麻…」 「あ…っ、イ…アアアッッ!!」 風のざわめきに紛れて、龍麻の声が犬神の耳の奥でこだました――…。 「せんせ〜…おんぶしてください〜〜」 ベンチに座ったまま、強請るように両手を差し出してきた龍麻。 そのまま放っておこうかとも思ったのだが、先程の行為を考えると、そうもいかない。 犬神は龍麻を何度も抱いた。龍麻の意志などお構いなしで、自分の欲求のままに抱き続けた。 そのお陰で犬神は十分満足したのだが、当の相手は精も根も尽き果てたという感じで、立つ気力もないらしい。 「…ほら、背中に乗れ」 「はぁ〜い」 龍麻は力なさ気にうなずくと、犬神の背中に身を預けた。 こういう子供っぽい龍麻を見ていると、自分が父親になったような気分にさせられる。…何とも複雑な心境だ。 犬神に軽々と抱え上げられた龍麻は、その背中に頬を寄せた。 「ねぇ、先生…。僕がニセモノの<先生>と闘ったみたいに、先生の所にも<僕>が出たんですよね?」 「ああ」 「その時…少しは僕みたいに『どうしよう』とかって思わなかったんですか?」 「当たり前だ」 「恋人の姿をしてたのに…?全然迷いはなかったっていうんですか?」 「あるわけがない」 「――そう、ですか…」 龍麻の手が背広をギュッと掴む。そう応えた彼の声はひどく弱々しく悲しげだった。 自分が期待していた返事とは違った答えに、龍麻は淋しさを覚えた。 贋者の<犬神>と対峙した時、自分は犬神のように割り切ることができなかった。 贋者だとわかっていても、愛する人の姿に傷をつけることに躊躇いを感じずにはいられなかった。 それと同じ思いを、犬神も感じてくれていたのだろうと思っていたのに――。それをあっさりと否定されてしまったのだ。 「恋人」という肩書きを持つ自分の存在が、犬神にとってどれほどのものなのだろう? 少しの迷いもなく一刀両断できるほど、彼の中にある自分の存在意義はちっぽけなものなのだろうか? ――そう思うと、無性に悲しくて、悔しくて…再び目元が熱くなった。 「へ、へへ…やっぱり…僕ってまだ未熟者ですね…。先生みたいに強くは――なれないや…」 「…」 涙を堪えて笑う龍麻を、犬神は背中越しに感じていた。その証拠に彼の喋りが少し震えていて、自分の背広を掴む力がさらに強くなっている。 そんな龍麻に犬神は振り向かずに鼻で笑った。 「――俺が迷わずアイツを殺せた理由を教えてやろうか?」 「…??」 「本物の龍麻の方がずっと可愛い」 「えっ…?!」 今までに聴いたことのないような犬神の台詞に、龍麻は声もなくただ驚いていた。 これまでに犬神の口からこのような褒め言葉を聞いたことがあるだろうか…いや、ないだろう。 犬神の発した言葉は嘘ではない。 あの時犬神は、瞬時に目の前にいる者が本当の<龍麻>ではないと悟った。 醸し出している雰囲気がすでに本物の<龍麻>とは異なっていたのだ。 あの愛らしさは誰にも真似できない。だからこそ、即座に見抜くことができたのだと思う。 犬神は、流石に自分でも赤面モノなことを口走ってしまったと思い、咳払いをしてその場を濁した。 柄にもなく小恥ずかしくなって、後ろなど到底振り向けない。 「――ということだ。だからメソメソするな」 「メッ、メソメソなんてしてませんっ」 「嘘つけ。今にも泣きそうな顔をしてるクセして」 「えっ、本当ですかっ?!」 「ホラ見ろ。図星じゃないか…」 思わず吹き出して、肩を震わせる。 「ひ…ひっどぉい!騙しましたねぇ〜!?」 「騙される方が悪い」 「むーっ!先生のいけずぅ〜っ!!」 「ぐっ、お、おいっっ!首にしがみつくなっ…ク、苦し…うぐっ」 龍麻が犬神の首に腕を絡めて締め付けてくる。それが結構キツくてむせてしまう。 だが犬神がいくら言っても龍麻の腕は余計締め付けてくるばかり。 「犬神先生のバカ〜〜ッ!」 「オ…マエはっ…人を殺す気かぁっっ!?」 「バカバカバカバカ〜〜〜〜〜〜ッッ!!」 「いい加減にしろーーーっ!!」 ほんわかとした月明かりの下、中年男性と少年の叫びが轟いた。 この後の二人がどうなったかは、満月のみぞ知る――…。 End. |
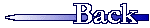 |
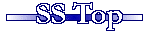 |